コスパの良い高性能CPU Ryzen7 2700Xを購入してから2年半。このときは、CORE i9 9900Kのベンチマークスコアに自作PC界隈がざわついていた頃だったと思います。
しかしながら半導体の時代の流れはあまりにも速いもので、とうとう先月Intel CORE(TM) i9 12世代が発売されました。これは前世代のi9を圧倒するだけでなく、勢いに乗っていたRyzen Gen3すらも置き去りにするシングルスレッド&高コスパなマルチスレッド性能で再び自作PC界隈がざわついています。
当初はマルチスレッド性能に惹かれて購入したRyzenでしたが、1年前からOpenVINOなどのIntel最適ツールやシングルスレッド性能の低さ、Windows11によってRyzenじゃなくてIntelがいいなーやっぱ…となってきたました。
そして、今月発売されたので、CPUクーラーのLGA1700対応に合わせて購入しました。(2ヶ月前にiPad買ったばっかなのに!)
届いた pic.twitter.com/FYL5cbX3NM
— Ar-Ray (@Ray255Ar) 2021年11月19日
購入したもの
次のものを購入しました。
メモリ:DDR4 32GB 3200MHz x2(前:HyperX 8GB 2400Hz x2)
クーラー:TUF GAMING LC240 ARGB(前:虎徹 MarkⅡ)
CPUの「KF」型番は内蔵GPUが搭載されておらず、外付けGPUが必要になります。
 | Intel Core i9 12900KF BOX 第12世代インテルCore i9プロセッサー GPU非搭載 CPU 価格:77,575円 |
![]()
 | ASUS TUF GAMING LC 240 ARGB Aura SyncとTUF Gaming 120 mm ARGBラジエーターファンを2基搭載したオールインワン水冷CPUクーラー 価格:14,948円 |
![]()
 | ASUS TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4 Intel 第12世代Coreプロセッサー対応 Z690チップセット搭載ATXマザーボード 価格:37,350円 |
![]()
組んだ
CPUなど部品は全てarkで調達しました。およそ16.5万円。GPUや電源が含まれていないので実際はもっと費用がかかります。
使用するパーツはこちらになります。

CPUをセッティングしてきます。取り付けはとても力がいる作業で、壊れるんじゃないかとひやひやしながら取り付ることに…

とりあえず一通り組み立ててWindows11で動作確認しました。この時点ですでにうまく動いていました。

バラして再び組み立て。

ケースは1年半前に購入した黒鴉を引き続き使っています。値段の割には質感がよいのでお気に入りです。
できれば大きいほうが好ましいですが、持ち運びする関係上できる限り小さなケースを使いたいけどRTXグラボ使いたいという要件を満たすケースを買いました。このケースだと240mm簡易水冷とATXマザーボードは入ります。
ただし、メモリの高さは注意しましょう。以前使っていた光るメモリは入りませんでした…(まさか水冷で干渉があるとは思わんでしょ❓)
 | SAMA JAX-03W 黒鴉 kurogarasu ミドルタワー PCケース サイドパネルに強化ガラス採用 価格:6,164円 |
![]()
また貯金したらTUFの持ち運びやすいケースも検討しています。
なかなかいい感じのゲーミングPCって感じじゃないですか?(実際はLinuxインストールしてビルドとシミュレーションするんですけどね。)
光っている電源の正体はこれ。前回のPCアップデート記事でも取り上げた超花電源です。品質の良さから自作PC勢に人気の電源らしいです。
光らないほうもあります。どちらも高いですが電源でPCが落ちるよりはマシです。
結局主要パーツがASUSづくしの構成になっちゃいました。仮にこれを全てほぼ定価で揃えると大体38万円くらいになります。(実際はそれよりも高くなる可能性すらある)
| 項目 | パーツ名(Amazonやホームページのリンク付き) | 補足 |
|---|---|---|
| CPU | [Intel Core i9 12900KF | ビデオ出力なし |
| マザーボード | TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4 | DDR4対応 |
| メモリ | SK Hynix 32GBx2 DDR4 3200MHz | DDR4 |
| GPU | ROG-STRIX-RTX2080TI-O11G-GAMING | RTX3070Ti相当 |
| 電源 | SUPERFLOWER 850W GOLD | 光る |
| SSD(Ubuntu用) | Samsung 870 QVO 1TB SATA | SATA接続はOS切り替えのため |
| ケース | SAMA 黒鴉 | ミドルタワー |
| CPUクーラー | TUF-GAMING-LC-240-ARGB | |
| ケースファン | IN WIN Sirius Loop |
私は、RTX2080TIだけ中古を9万円で購入しているのでそこでかなり費用を抑えています。2080TIよりも高性能かつVRAM 11GB以上を購入できるのはRTX 3080TI(25万円)とRTX 3090(30万円〜35万円)くらいしかないので、昨年の判断はとても良かった。
グラボを購入した記事はこちらから↓
性能(Windows 11)
さて、気になるのはその性能です!他のCPUの実性能の比較はプロの方の動画などを見たほうが良いと思いますが、こちらは研究用途なのでその使用感についてちょっと見ていきます。
ただ、Windows11はOfficeソフトとWSLgの検証くらいにしか使わないのでベンチマークだけ行ってさっさとUbuntuに切り替えていきます。
あ、Aviutlはある。でもそのベンチマークないなー。
まずはシステムモニタの様子から
CPU。圧巻の24スレッド。

画像をよく見ると下の8窓にタスクが集中していることが分かります。
これは偶然じゃなくてOS側が効率重視のEコアに集中させているからだそうです。動画配信などの処理数増加時のサポートをしてくれるみたいです。
次はメモリ。64GB!これでDockerやバーチャルマシンを動かしまくっても枯渇する心配はなさそうです!
DDR5は実質入手不可能ですが、3200MHzで動いてくれるので大丈夫でしょう(!?)

ベンチマークを測定しました。使用したのはレンダリングベンチマークとして有名なCINEBENCH R23。

ずっとR15ばっか使っていたので初めて知ったのですが、最近のCINEBENCHは一度走らせたら10分間走りっぱなしなんですねー。
スコアは以下の通り
マルチ:25726
シングル:1986
これは、DDR5やら高級マザーやらをつかったCore i9 12900Kと同様の環境におけるCore i7 12700Kの間くらいの値らしいです。最新のRyzen 9 5950Xにも迫るマルチスレッド性能と圧倒的なシングルスレッドが魅力的です✨
CINEBENCHスコア一覧は以下のリンクから。
i9 12900KF、結構冷えてる。
数値を測るなどの検証をしているわけではないですが、CPU温度は取れているので報告。
使用したのは TUF-GAMING-LC-240-ARGB 「A」がついている方を買わないとLGA1700対応のものが買えないそうです。紛らわしいので注意。
CINEBENCH R23(10分間):230W、86〜89℃
「i9は爆熱だぞ」とはよく言われていますが、240mmの簡易水冷でも相性が良ければ十分冷える印象を受けました。大げさなんだよ。
Ryzen7のときは虎徹を使っていてケースがめっちゃ熱くなっていましたが、このクーラーはそんなことはなくむしろ静音になってます。すごい。
Ubuntuとの相性(良くない)
結論を先に言っちゃっていますが、正直12世代IntelはWindows11ありきの設計だと思います。とくにPコアEコアの使い分けなんてOSをいじらないとできない技術らしいので。
べつにEコアの性能が低いわけではないのですが、シングルスレッドで処理するような処理だとUbuntuは高負荷な処理を行うコアを5〜10秒ごとに変更する仕様があるので、処理するコアがPコアからEコアに移動した途端に性能が低下する可能性があるということです。
関係ないかもしれませんが、darknet-rosのMAX-FPSとMIN-FPSの振れが大きい気がします。
darknet-ros-fp16、実はCPUの性能重要だった説👀
— Ar-Ray (@Ray255Ar) 2021年11月20日
YOLOv4-tiny-416にて
・Ryzen7 2700X :167fps〜149fps
・Intel i9-19200KF:224fps〜113fps
OSがPコアとEコアの使い分けをしていないので、性能が振れが激しい説はある。 pic.twitter.com/kn0MmVd5ee
コンパイルは期待通り速いです。OpenCVのコンパイルなら-j24以外のオプションなしで2分40秒で処理しちゃいます。ちなみに、前のRyzen7なら3分半、ノートPCなら30分、ラズパイなら1時間以上です。
OpenCVのコンパイル(オプションなし・Contribなし)
— Ar-Ray (@Ray255Ar) 2021年11月20日
real2m49.586s
user56m59.775s
sys2m32.656s
i9やばすぎ
ちなみに、OpenVINO系統のリアルタイム処理がめっちゃ速くなるのかなーと思ったのですがそれは期待はずれ。YOLOX-Nano (OpenVINO) が40fps程度しか出ませんでした。CPUも全然使ってくれませんでした。
このPCはほとんどの時間をUbuntuで運用し、動画編集やゲームには使用しません。配信の時間と才能があれば、VTuberのようなアバターを動かしてゲームしながらOBS配信なんて楽勝なんだろうな〜。
なぜオーバースペックなスペックでPCを組むのか?(持論)
配信しない限り、ゲーム用途だとi5でも十分と言われています。ほとんどの大学生はさらに消費電力の低いノートパソコンでプログラムを書いてコンパイル・プログラム実行をします。
それならi9もいらないのでは?と思われるかもしれません。
もちろん、高性能PCにしたのはコンパイル時間を短縮したりシミュレーションをスムーズにすることが目的ですが、それ以上の意味があると思います。
それは私が怠け者だからです。むしろ、怠け者だからこそ高性能なやつを購入しています。
怠け者だとつぎの困ったことなどが起こります。
PCがカクついたり止まるとやる気が下がる
コンパイルが遅いと検証が長引くのでストレスがたまる&時間を持て余す←有効に使えばいいじゃん(有効に使えない)
「どうせ安いPCだし…」と自分の能力不足をPCのせいにする
高性能PCはこれらを解決させることができます。
カクつく→少なくとも論文に乗ってるやつを実装しても問題ないのでやる気が下がらない。
コンパイルが遅い→ほとんどすぐ終わるのでストレスがたまらない。
どうせ安いPCだし→めっちゃ高いので有効活用しようと思うようになる。
あとは、擬似的に未来のi7を先行購入できます。コンパイル時間は短ければ短いほどいいです。
誰もビルドしたことのない組み合わせを試す場合は、短い時間にエラー文をどれだけ読めるかによって作業進捗が変わっていくので、結局どれだけ性能が高くても足りないというわけです。プログラミングするなら高性能PCを!
…どうしよう。アルバイトしないと。
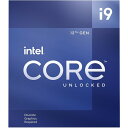 |
![]()
 |
![]()